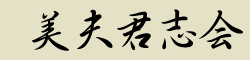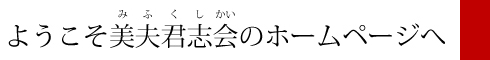機関誌『美夫君志』
美夫君志会にて編集、発刊している学術雑誌です。
| 創刊号~第20号| | 第21号~第40号| | 第41号~第60号| | 第61号~第80号| |
| 第81号~第100号| | 第101号~| |
第80号(平成22年3月) |
|
|---|---|
| 研究 | |
| 『万葉集』における七夕歌の意義 ―季節の景物としての七夕― | 大浦 誠士 |
| 巻十七の構想 ―冒頭三十二首の役割について― | 市瀬 雅之 |
| 紀女郎歌と仏教 | 大脇由紀子 |
| 倭建命考 ―天皇と伊勢大神の紐帯として― | 岡本 恵理 |
第79号(平成21年12月) |
|
| 研究 | |
| 家持歌「悲しけくここに思ひ出」考 ―上代における形容詞ク語法の役割― | 山口 佳紀 |
| 巻六の構想 ―活道の岡に集う歌を一例としながら― | 市瀬 雅之 |
| 『万葉集』巻十二・二九〇六番歌の発想 | 小田 芳寿 |
| 大伴家持の応詔儲作歌 ―君臣像の特色とその意義― | 鈴木 道代 |
第78号(平成21年3月) |
|
| 研究 | |
| 『古事記』沙本毘古王の反逆と天皇の歴史 | 梅田 徹 |
| 皇位継承の確定 ―允恭記における穴穂御子と大前小前宿禰― | 井ノ口 史 |
| 舎人慟傷歌群における烏の機能 | 朴 喜淑 |
| 万葉集末四巻の伝聞歌 ―家持歌日記の方法― | 松田 聡 |
第77号(平成20年12月) |
|
| 研究 | |
| 万葉集伝来史における片仮名訓本の位置 ―平安期片仮名訓本との関係― |
田中 大士 |
| 「新しき年のはじめ」 ―天平十四年正月十六日続日本紀歌謡と万葉歌― | 塩沢 一平 |
| 日本古代の漢字使用にみられる類化による 偏旁冠脚の添加・置換をめぐって ―正倉院文書の例を中心に― |
井上 幸 |
| 史料 | |
| 美夫君志会七十年の歩み | |
第76号(平成20年3月) |
|
| 研究 | |
| 人麻呂歌集七夕歌の「告」 | 鉄野 昌弘 |
| 筑前国の志賀の白水郎の歌十首について | 村田右富実 |
| 「万代にかくしもがも」 ―笠金村「神亀二年の吉野讃歌」についての考察― | 倉持しのぶ |
| 家持の難波宮讃歌(下) ―「陳二私拙懐一一首」の讃美の方法と表現― | 奥村 和美 |
第75号(平成19年11月) |
|
| 研究 | |
| 木簡として見た歌木簡 | 栄原永遠男 |
| 家持の難波宮讃歌(上) ―「陳二私拙懐一一首」の讃美の方法と表現― | 奥村 和美 |
| 山上憶良「令反或情歌」について | 廣川 晶輝 |
第74号(平成19年3月) |
|
| 研究 | |
| 歌の連接 ―巻八の場合― | 原田 貞義 |
| 万葉集の地名表記について ―国名を中心に― | 北川 和秀 |
| 女歌の役割 ―対詠性の問題から― | 佐野あつ子 |
| 万葉集巻九の配列について | 村田右富実 |
第73号(平成18年11月) |
|
| 研究 | |
| 大伴家持のコミュニケーション技法 ―ふたつの宴席詠を事例として― | 影山 尚之 |
| 『万葉集』の菟原娘子伝説歌 ―〈墓〉の表現性― | 廣川 晶輝 |
| 『古事記』のイハノヒメ物語 ―大后の権威放棄と回復の物語― | 小山 眞弥 |
| 助辞「之」の様相 ―『萬葉集』中の散文例を対象に― | 廣岡 義隆 |
第72号(平成18年3月) |
|
| 研究 | |
| 大伴坂上郎女たちの「梅花」 ―「梅花落」から出発した倭歌― | 佐藤 隆 |
| 月と譬喩 ―満誓「月歌」を中心に― | 中嶋 真也 |
| 石上乙麻呂の「舊識」に贈る詩と「麗人」を想う詩と | 渡邉 寛吾 |
| 「万代にかくし知らさむ」 ―笠金村「養老の吉野讃歌」についての考察― |
倉持しのぶ |
第71号(平成18年2月) |
|
| 研究 | |
| 飛鳥の地名を発掘する ―山田道のアルケオロジー― | 大脇 潔 |
| 万葉集巻十五遣新羅使人歌群の編者をめぐって ―冒頭十一首贈答歌群の検討― |
村瀬 憲夫 |
| 遣新羅使歌の「挽歌」(下) ―天平期において「挽歌」とはいかなるものであったか― |
梶川 信行 |
| 鳴く鹿を詠む歌 ―詠物長歌の位相― | 井上さやか |
第70号(平成17年3月) |
|
| 研究 | |
| 「歌の文字化」論争について | 犬飼 隆 |
| 遣新羅使人歌群「當所誦詠古歌」の位相 | 大浦 誠士 |
| 遣新羅使歌の「挽歌」(上) ―天平期において「挽歌」とはいかなるものであったか― |
梶川 信行 |
第69号(平成16年11月) |
|
| 研究 | |
| 「島の宮」の「島」新考 | 渡瀬 昌忠 |
| 古代地方社会と文字 | 平川 南 |
| 廣瀨本万葉集校合書入考 | 北井 勝也 |
| 懸詞的用法における文字選択 ―人麻呂の序詞を中心に― | 八木 京子 |
第68号(平成16年3月) |
|
| 研究 | |
| 上代の清濁と語彙 ―オホ~・オボ~(イフ~・イブ~)を中心に― | 蜂矢 真郷 |
| 古事記の「崩」に関する一考察 | 阪口 由佳 |
| 防人歌「駿河国・上総国歌群」の成立 ―「進上歌数」との関連から― | 東城 敏毅 |
| テクストとしての『類聚歌林』 | 市瀬 雅之 |
第67号(平成15年11月) |
|
| 研究 | |
| 「放逸せる鷹」の歌 ―耽溺の美学― | 菊池 威雄 |
| 万葉集の皮膚感覚、生理感覚 ―歌語サムシの確立― | 影山 尚之 |
| 萬葉集の嗤笑歌 | 橋本亜佳子 |
| 続紀宣命における天皇像の変貌 | 平松 秀樹 |
第66号(平成15年3月) |
|
| 研究 | |
| 『遊仙窟』古訓を『萬葉集』歌に溯る | 内田 賢德 |
| 麻續王伝承の転生 ―八世紀の《初期万葉》 | 梶川 信行 |
| 日本琴「贈答書簡」 ―藤原房前の返書を中心に― | 同前 美希 |
| 遣筑紫諸国防人等歌 ―防人集団の肩書きと序列― | 小林 宗治 |
第65号(平成14年10月) |
|
| 研究 | |
| 交友と景物讃美 ―家持と池主の贈答を中心に― | 菊池 威雄 |
| 人麻呂歌集と「正述心緒」 | 大浦 誠士 |
| 「にほひてゆかな妹も触れけむ」 ―人麻呂歌集巻九・一七九九歌の助動詞ケムの表現するもの― |
月岡 道晴 |
| 近代における『万葉集』研究史の一断章 ―上田萬年をめぐって― | 野口 恵子 |
第64号(平成14年4月) |
|
| 研究 | |
| 魂と心と物の怪と ―古代文学の一側面― | 多田 一臣 |
| 「我が欲りし野島は見せつ」 ―万葉集巻1・一二番歌の解釈をめぐって― | 倉持しのぶ |
| 「藤原宮●民作歌」考 ―役民の登場をめぐって― | 林 慶花 |
| 巻四・五〇九の「淡路」「粟島」に関する一考察 | 上谷内 勉 |
第63号(平成13年10月) |
|
| 研究 | |
| 古代人のこゑ(声)を聞く | 釘貫 亨 |
| 妹がみためと私田刈る(巻七の一二七五) ―旋頭歌の笑い― | 上野 誠 |
| 笠金村吉野讃歌の方法 ―九二〇~九二二番歌を中心に― | 中嶋 真也 |
| 奈良時代における『法華経』依拠の考察 | 遠藤 慶太 |
第62号(平成13年4月) |
|
| 研究 | |
| 「ゆつ磐群に 草生さず」考 | 村田右富実 |
| 山部赤人の「過勝鹿真間娘子墓時」歌 ―その表現の特質について― | 井上さやか |
| 越中における「おもふどち」の世界 | 新沢 典子 |
| 江家本万葉集逸文考 ―伝来と本文について― | 北井 勝也 |
第61号(平成12年11月) |
|
| 研究 | |
| 藤原八束歌二首の意図 ―春日と春日野― | 吉村 誠 |
| 万葉相聞表現としての「夢」 ―「俗信の夢」と「自分ゆえの夢」― | 菊川 恵三 |
| 「橘の寺の長屋」と「橘の照れる長屋」 ―万葉集巻16・三八二二~三八二三の歌と説話― |
影山 尚之 |
| 人麻呂献呈挽歌の「不寐者」 ―異文歌と本文歌― | 伊藤 延子 |